はじめに
「外来種って本当に問題なの?」「対策はどうなってるの?」そんな疑問をお持ちの方必見です。
2025年8月23日、手柄山交流ステーション(兵庫県姫路市)で開催された企画展「ここが知りたい!外来生物の本当の問題」の関連イベントとして、国立環境研究所生態リスク評価対策研究室長・五箇公一先生による講演会が行われました。
1時間にわたってノンストップで淀みなく語られた内容は、専門知識と豊富なエピソードに満ちた圧巻の講演。本記事では、その内容を詳しくレポートします。
五箇公一先生とは?プロフィールと研究内容
五箇公一先生は保全生態学の専門家として、ダニの研究をはじめ外来種対策の最前線で活躍される研究者です。
経歴
- 1996年:博士号取得
- 現職:国立環境研究所生態リスク評価対策研究室長
- 専門:保全生態学、ダニ類研究
- メディア出演:NHK「クローズアップ現代」、「全力!脱力タイムズ」など多数
驚くべきことに、先生の本業であるダニの研究成果は上皇陛下にも説明する機会があり、その拡大図が皇室に飾られているという名誉についても講演で言及されました。
【衝撃の事実】日本の外来種問題、すべて一人の学者が原因?
キングギドラ研究から見えた多様性の重要性
講演の冒頭で紹介されたのは、先生の意外な趣味。オフィスに所狭しと並ぶ怪獣フィギュア、特にお気に入りは三つ首の宇宙怪獣「キングギドラ」です。
この趣味が思わぬ研究に発展したエピソードが披露されました。キングギドラ生誕60周年を記念して、2020年に発見された新種のカマキリ「キミドリシリス・キンギドライ」の学名について真面目に検証した論文を執筆。昭和と平成のキングギドラの体型を比較し、「とても同一種とは言えない」という結論を導き出し、国際学術誌「BioScience」に掲載されたそうです。
明治時代の「失敗三部作」- 渡瀬庄三郎の負の遺産
講演で最も印象的だったのは、日本の代表的な外来種問題のほとんどが一人の学者によって引き起こされたという驚愕の事実です。
講演では「東京大学の大先生」として紹介された人物について調べたところ、**東京帝国大学教授で日本動物学会会長も務めた動物学者、渡瀬庄三郎氏(1862-1929)**でした。
渡瀬庄三郎が導入した問題の外来種
- マングース(1910年)
- 目的:ハブ退治のため沖縄に17頭を導入
- 結果:ハブは夜行性、マングースは昼行性で遭遇せず
- 被害:在来種のヤンバルクイナ、アマミノクロウサギを捕食
- ウシガエル(1918年)
- 目的:食用として輸入
- 当時の効果:戦後の食糧難時代には重要な蛋白源
- 現在の問題:誰も食べず、在来生物に深刻な被害
- アメリカザリガニ
- 目的:ウシガエルの餌として同時導入
- 現在の状況:野生化し、生態系に深刻な影響
講演では「なんでこんなに餌が好きだったんだろう」「明治開国の時代にあって強い外来種導入で強い国家を作るという命題があった」と説明されました。調べると渡瀬氏は「渡瀬ライン」で有名な優秀な学者でしたが、外来種導入については完全に裏目に出てしまいました。
生物多様性とは?なぜ重要なのか
4つの階層で理解する生物多様性
- 遺伝子の多様性 – 一つの種の中での遺伝的差異
- 種の多様性 – 様々な種類の生物が存在すること
- 生態系の多様性 – 森、川など異なる生態系の存在
- 景観の多様性 – 地域ごとの環境や文化の違い
人間社会への直接的影響
生物多様性は私たち人間の生存基盤そのものです:
- 生命維持機能:きれいな水、空気、食料の供給
- 社会・文化の基盤:地域ごとの独自文化の発展
- 経済活動の基礎:観光、農業などの産業
重要なポイント:生物多様性の保全は「生き物がかわいそうだから」ではなく、人間社会の持続的発展のために必須なのです。
【現在進行形】深刻化する外来種問題
ペット由来の外来種被害
アカミミガメ(元ミドリガメ)
- 導入経緯:ペット用として大量輸入
- 問題:飼いきれずに放流される事例が多発
- 対策:2023年から条件付き特定外来生物に指定
アライグマ
- 導入経緯:1970年代のアニメブームで年間1500匹輸入
- 飼育の現実:気性が荒く飼育困難
- 現在の分布:北海道から九州まで拡大
【警告】人獣共通感染症のリスク
アライグマは北米では狂犬病の主要媒介動物です:
- 日本は1960年以降狂犬病ゼロ国を維持
- しかし中国など近隣国では発生継続中
- リスク:アライグマが媒介すれば日本でも再発の危険
現在、飼い犬の狂犬病予防接種率が70%まで低下しており、二重のリスクを抱えています。
水辺の外来種問題と「転校生効果」
オオクチバス(ブラックバス)の脅威
- 原産地での状況:アメリカでは天敵や競合相手が存在し、個体数は安定
- 日本での暴走:圧倒的優位に立ち在来魚を捕食
- 「転校生効果」:環境が変わることで本来の能力が発揮される現象
都市部特有の問題:熱帯魚の越冬
温排水により冬でも16℃以下にならない水域が都市部に存在:
- 本来越冬できない熱帯魚が定着
- 家庭排水処理の向上で水質は改善したが、水温は上昇
【成功事例】最新の外来種対策技術
マングース駆除:世界に誇る根絶成功
- 技術:「マウスバスターズ」専用捕獲器を開発
- 成果:奄美大島で2018年から捕獲数ゼロを達成
- 結果:統計学的に99.9%駆除完了と判定し、2022年に根絶宣言
ブラックバス対策:繁殖阻止作戦
- 人工産卵床:産卵習性を利用した卵の回収システム
- 効果:宮城県での試験で個体数減少と在来魚回復を確認
アライグマ対策:行動を利用した捕獲
- 筒型トラップ:木の洞に巣を作る習性を利用
- 効果:餌なしでも高い捕獲効果
- 最新技術:不妊化ワクチンによる個体数制御も開発中
【緊急課題】昆虫の外来種問題
ヒアリ対策の現状
2017年に日本で初確認以降、継続的に侵入しているヒアリ:
開発された対策技術
- スプレー法:家庭用殺虫剤の組み合わせでコンテナ消毒
- ベイト剤:講演では「とんがりコーンが大好物だった」として開発されたが、東ハト社からクレームが来て現在は「スナックフル」と呼んでいるとのユニークなエピソードも紹介
中国産スズメバチの脅威
- 侵入地域:長崎県対馬
- 被害:ミツバチを好物とし養蜂業に深刻な被害
- リスク:九州本土への拡散の恐れ
クビアカツヤカミキリ:桜の敵
- 被害:桜の木を食害
- 海外対策:ヨーロッパでは被害木の全伐採で根絶達成
- 日本の課題:桜への愛着が強く同様の対策は困難
植物の外来種:オオバナミズキンバイの脅威
駆除困難な理由
- 原産地:南米
- 特徴:根や切れ端からでも再生する強い繁殖力
- 問題:機械による駆除で切れ端が拡散し被害拡大
グローバル化時代の感染症リスク
カエルツボカビ病の教訓
- 発生時期:1990年代から世界中で両生類の大量死
- 日本への侵入:2006年に確認
- 対策:PCR検査による監視体制を構築
- 研究成果:世界各地のDNA分析で感染経路を解明
COVID-19予測的中のエピソード
講演者は2019年から「2020年オリンピックで新しいウイルス侵入の恐れ」と警告していました。感染症問題は厚生労働省だけでなく、環境問題としても重要な課題であることを示しています。
まとめ:私たちにできること
外来種問題の現実
- 生物多様性の破壊を通じて人間社会の基盤を脅かす
- グローバル化により今後も深刻化する見込み
- 科学的な対策技術の開発と実用化が進んでいる
効果的な対策の原則
- 予防(持ち込み防止)が最も重要
- 早期発見・早期駆除が効果的
- 継続的な監視が必要
個人でできる対策
- ペットを最後まで責任を持って飼育
- 絶対に野外に放さない
- 外来種問題への理解を深める
- 地域の対策活動に協力
さいごに
五箇公一先生の講演を通じて、外来種問題が私たちの生活に直結する深刻な環境問題であることがよくわかりました。一人の学者の判断が100年後の生態系に影響を与える事実は、私たち一人ひとりの責任の重さを教えてくれます。
関連記事
記事情報
- 講演日:2025年8月23日
- 会場:手柄山交流ステーション(兵庫県姫路市)
- 講演者:五箇公一氏(国立環境研究所生態リスク評価対策研究室長)
- 関連:企画展「ここが知りたい!外来生物の本当の問題」
タグ: #外来種 #生物多様性 #環境問題 #五箇公一 #国立環境研究所 #アライグマ #ヒアリ #講演レポート

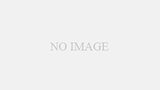
コメント